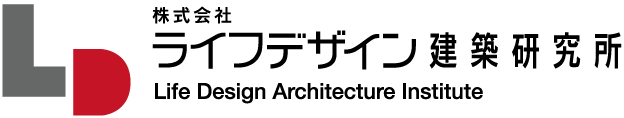Column
コラム
設計事務所にとって、6月は新年度の仕事が一斉に始まる時期です。弊社も継続事業、新たな物件の相談、そしてプロポーザルコンペ。
プロポーザルコンペは、大いに参加したいのですが、参加条件が厳しかったり、スケジュールの都合で断念したり。
そしてコロナ禍、急激に普及したのがオンライン打ち合わせ。講演会や勉強会、海外との打ち合わせには最適ですが、多数が参加する会議には不向きだと感じています。
また建築設計では、詳細はやはり原寸図でなければわからないものが多くあります。
最近では、コロナもかなり終息したこともあり、直接会う打ち合わせ+オンライン会議と、毎日が打ち合わせだらけで、デスクワークが進まないことも痛感しています。
茂木聡
令和4年の新年度が始まりました。設計事務所にとっては、新年度は各作業の継続中のため、年度という区切りは無いのですが、一般社会は新年度という区切りの時期にあたります。
弊社は積極的に学生アルバイトを募集し、一緒に建築をつくることにより、学生にとってより現実的に設計の世界を知ってもらう試みを、会社創設時より行ってきました。
アルバイト卒業生は、現在、日本のみならず、世界で活躍しています。皆一流企業で活躍しています。我々スタッフもうれしい限りです。また学生から様々な刺激をもらいます。
アルバイト学生は、地域柄県内の学生に限定されてしまいますが、秋田県立大学、秋田美術工芸大学、秋田高等専門学校の方々です。現在も皆さん、頑張っています。
興味がありましたら、遠慮なく声をかけてください。
弊社は、引き続き今いただいている仕事の邁進、そして新たに始まるであろうプロポーザルコンペに積極的に応募して行きます。
引き続き、皆様のご支援を期待する次第です。
ロシアのウクライナ侵攻が連日話題になっています。日本とロシアの地勢的距離を考えると、対岸の火事とは言えないでしょう。
現代の戦争がどういうものか、あらためて考えさせられます。国という概念は何なのか、自治があり、それがせ世界各国から認められ、独立として運営されるものと考える時、国の定義があまりにも曖昧であることに気が付かされます。世界が米ソの冷戦時代を過去のものとした今、世界がグローバル化した時に起こった戦争。日本では感じえない陸続きでありながら国境がある。私たちはヨーロッパを旅行した時、国境をあまり意識せずに移動できます。ひとたび戦争がはじまると、国というものが全面に出てくる。不思議な概念です。
私は日本で生まれ育ったので、国境というものを意味あるものと感じない。日本という国が戦争を経験し、自国を守るために多くの人間が亡くなった事実、これはとても重いことなのだけれど。
今、インターネットの世界には、国境は存在しない。確かに国にっては自由にネットを検索できない事実もあります。しかし、我々が知るインターネットの世界は、全体を100とすると、約5の世界。つまり各国が規制する世界は、その5の部分。大方は規制外の世界。
今、戦争で多くの人が亡くなっている。これは一般国民に限らず、兵士も。
新型コロナウイルスの世界蔓延で、国境の意味が無いことは、世界中が痛感したこと。
どんな結末が待っているのか、わかりませんが、世界は確実に変わっていることを痛感します。 茂木聡
医療・福祉施設の設計を多く手掛けていると、物理的動線としての死は、絶えず考えます。しかし、実際の死は、ここに無限大の世界をもって存在しています。私は比較的早く、両親を亡くしました。その時は私の子供たちも小さく、日々の生活に追われ、また同居していなかったこともあり、死にたいする実感がつかめなかったと感じます。仕事仲間の友人のお母さまが亡くなったとの訃報を聞きました。九十歳後半。しかし、彼の追悼の文章を見て、思わず涙してしまいました。その背景を垣間見ることができたからです。彼の日々の対応が、その生まれ育った環境にあったのだと知りました。
昨今、新型コロナ感染症の蔓延もあり、新聞誌上では、今日は何人が亡くなったという記事を眺めています。しかし、その一つ一つに、人生があり、関わってきた人々が大勢いること。余りに無関心でいる自分に、恥ずかしさを覚えました。
建築設計の原点は、人が生きていく器を造ること。こと一番大切な部分が、昨今抜け落ちてしまったように感じます。 茂木聡
2022年、新年を迎えました。
昨年は、設計プロポーザルコンペでは、新たな挑戦をしましたが、結果が出ない年でもありました。
結果は1勝5敗。大きなものは、全敗という結果でした。
意欲的挑戦が多かった分、勝敗に左右したこともあったと思います。
また、コンペへの参加条件も厳しくなってきました。
以前は、秋田市主催の場合、特殊案件でなければ、弊社は参加条件を満たしていたのですが、以前から参加の準備を進めていた物件は、参加条件を満たさず、戦いにも参加できませんでした。人口減少に伴う、仕事の激減は、コンペの参加要件にも影響してきたようです。
事務所改革が必要な時代になったということでしょう。
一昨年、スタジオキャップと合併しました。
今年は、新たなスタッフを求めていかなければならない状況です。
若手のスタッフも必要です。
育成にも力を入れる必要があります。
まずは、現状勢力の力量アップから始めていきたいと考えています。
これからの数年間は、設計事務所の生き残りをかけた時代になると思います。
時代の流れは、想像以上に早く進んでいます。
今年一年、全力で頑張っていきます。
皆様の応援を、よろしくお願いいたします。
茂木聡